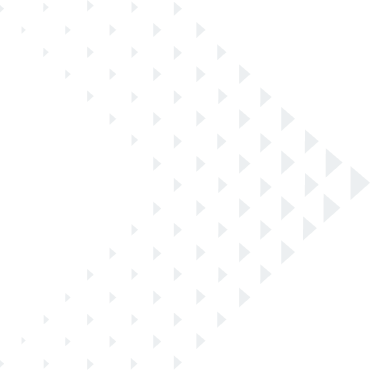オフショア開発


28/02/2023

3 minutes
失敗事例から学ぶ、オフショア開発成功への9つのヒント
昨今、ITシステム開発の現場では、オフショア開発という選択肢は一般的となりました。しかし、中には当初に想い描いた通りにはプロジェクトを進めることができなかったという声も聞こえてきます。そこで、本記事では、オフショア開発の失敗事例から学ぶ、失敗原因や成功へのヒントにについて紹介します。 オフショア開発で陥りやすい失敗事例 まずは、オフショア開発での失敗事例としてよく耳にする話題をいくつかご紹介します。 失敗事例1:仕様伝達に失敗し、納期が遅延してしまった 発注元の担当者は、発注先のオフショア開発会社に日本語ができるブリッジSEをアサインしてもらい、仕様と作業内容を文書にまとめてブリッジSEとミーティングを行って説明した。 ミーティングは日本語で行ったが、ブリッジSEも要求をよく理解してくれているように見えたため、日本語のコミュニケーションでも問題ないと判断していた。その後の進捗状況の確認でも、ブリッジSEからの報告は常に「問題なし」という回答があり安心していた。 しかし、次第にブリッジSEから1日に数回の質問が毎日のように届くようになった。担当者はその質問への回答作業に追われる日々となってしまい、レビューによる品質確認を行う時間を確保することができぬまま納期を迎えてしまった。 これは、オフショア開発会社への仕様の伝達がうまくいかずに作業の遅延が発生してしまったケースです。原因は、発注先の窓口となるブリッジSEとの日本語による意思疎通ができたため、仕様伝達のハードルは低かったと思い込んでしまったことにあります。 しかし、発注先のオフショア開発会社の窓口となるすべての人が技術面について知識を持っているとは限りません。 中には、主に通訳を役割とするコミュニケーターと呼ばれるべき人材にブリッジSEという肩書きを与えているオフショア開発会社も存在します。 このような失敗を回避するためには、窓口となるブリッジSEの日本語の言語能力の確認にとどまらず、そのブリッジSEの職務範囲や職能まで確認しておくことが大切です。 もし、オフショア会社の窓口担当者の技術的な内容の理解度に不安を感じる場合には、そのコミュニケーターを介して仕様伝達を行うのではなく、直接現地のSEと英語でやりとりを行う方がお互いの理解度を確認しながら進めることができるでしょう。その方が結果的には二度手間の発生を抑制でき、間接コストも削減することができるでしょう。 失敗事例2:度重なる仕様変更により、コストが増大してしまった 全体の仕様が確定しておらず、一部の仕様は暫定的なものとして見積を行い、そのまま見切り発車で発注した。 暫定部分は、発注後に五月雨式に仕様伝達を行ったものの、その後も仕様変更が繰り返され曖昧な仕様が残ったままだったため、ドキュメント作成やメールやチャットなどの仕様伝達の工数が増大した。 また、開発現場でも仕様の混乱や手戻りが発生し、当然スケジュールも大幅に遅延して収拾がつかなくなった。そのため、開発途中でブリッジSEと仕様確認の仕切り直しが必要となった。 その結果、コミュニケーションと開発の工数が増大し、最終的には、見積金額を大幅に超えてしまった。 これは、仕様が曖昧なまま発注したうえに仕様変更を繰り返した結果、コストと納期がオーバーしてしまったケースです。国内開発の発注においても発生し得るような例ですが、走りながら徐々に要求仕様を決めていくというやり方は、典型的な日本型の開発アプローチと言えます。 オフショア開発をこのような国内開発の感覚で行ってしまうと、信頼関係にひびが入ってしまい想像以上にトラブルを拡大させてしまう危険性があります。信頼関係がなければプロジェクトが失敗する確率は限りなく高くなるでしょう。そうなれば、金銭面でもトラブルに発展しまう可能性があります。 仕様を変更すること自体は問題ないのですが、問題は仕様変更をスムーズに進めるための段取りとコミュニケーションにあると考えられます。オフショア開発ベンダー側の状況を考慮して伝達することが大切です。 失敗事例3:日本語での意思疎通の失敗 ある過去に一度、開発を依頼したことがあるオフショア開発会社に、新規のプロジェクトを依頼した。初めて発注した際は、日本語でのコミュニケーションに多少の不安を抱いていたものの、アサインされたブリッジSEがとても優秀で、日本語スキルや技術レベルは事前の説明通りにレベルが高く、プロジェクトは無事成功を収める事ができた。 そこで、同じオフショア開発会社に別のプロジェクトを追加発注したところ、アサインされたブリッジSEの日本語スキルが低く、前回のブリッジSEと比較すると大幅に劣っていた。 事前に、コミュニケーション言語は日本語で行うとの取り決めていたものの、メールで質問を受け付けても一体何を伝えたいのか理解できないようなことがかった。そこで英文でのやりとりも試してみたが英語もさほど得意ではないらしく、結局、意思疎通はなかなか改善せず苦労した。 オフショア開発会社からの事前説明での「日本語コミュニケーションが可能な優秀な技術者が在籍している」との話に期待したところ、その事前期待が結果と異なっていて失敗したケースです。 たしかに、最初のプロジェクトにアサインされたブリッジSEは期待以上の能力を発揮してくれたため、次のプロジェクトでも期待するのは自然なことです。 初めての取引の際は、どこのオフショア開発会社もエース級の人材をアサインしてくるとうのはよくあることです。とはいえ、そのように優秀な人材が社内に多数在籍していて、発注者が希望するタイミングでいつでもアサインできるかどうかはまた別の話です。 このケースでは、エース級の人材は少数しか在籍していなかったり、または優秀な人材は別のプロジェクトに参加していて自社の案件にはアサインできなかったのかもしません。 顧客の要望に応じて、最適な人材を安定的にアサインできるかどうかは、オフショア開発会社それぞれの事情によって大きく異なります。特に、人材の豊富さは事業規模が大きいオフショア開発会社の方が有利でしょうし、また特定分野の人材であれば、小規模でもその分野に専門特化したオフショア開発会社なら最適な人材を確保できるかもしれません。 なお、日本市場に注力して事業を展開しているオフショア開発会社では、社内で日本語教育を行っていることは珍しくありません。しかし、その教育内容や方法も企業にとってさまざまで、営業やブリッジSEに限定して教育している場合もあれば、その他のエンジニアも含めて行う場合もあります。 また、日本語認定資格の取得を奨励し、資格取得手当てなどの制度を設けている企業もありますし、採用段階で選考基準として日本語のスキルレベルの高い人材や、日本国内でのビジネス経験や日本企業とのプロジェクト経験がある人材を多く採用しているケースもあります。オフショア開発会社選びの際には、そのような日本語教育のへの取組み状況状況も確認しておくとよいでしょう。 オフショア開発を成功に導くための9つのヒント 先述の陥りがちなオフショア開発での失敗事例のような問題は、実は日本国内での日本人エンジニアによる開発でも起こり得ることです。オフショア開発の現場では、とりわけ言語、文化、国民性の違いによるコミュニケーションのギャップが問題を生じさせる原因となる場合が多いです。そこで、ここではオフショア開発での失敗を回避し、開発プロジェクトを成功させへと導くための9つのポイントを紹介します。 1. コミュニケーション言語のスキルレベルを確認する 日本語や英語など、オフショア開発会社とのコミュニケーション言語を取り決める際には、コミュニケーションに支障がない程度の言語スキルを持っているかを事前に確認しましょう。 例えば、コミュニケーション言語を日本語にすると取り決めた場合、そのスキルレベルを客観的に把握する一つの目安としては日本語検定試験(JLPT)があります。日本語能力試験は、日本国内および海外で日本語を母語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定することを目的として行う試験です。試験はN1からN5レベルまでの5段階に分けられており、N1は最も難易度が高くなっています。 N1は幅広い場面で使われる日本語を理解することができるレベルで、N2は日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベルとされています。そうしたことから、外国人を採用する企業では、在留資格・ビザ取得の観点からもN1〜N2を選考基準としている場合が多いようです。 N1は日本語ネイティブでも満点を取るのが難しいレベルの試験と言われていますので、N1保持者であればビジネスシーンでの活躍を期待できるでしょう。しかし、必ずしもすべてのエンジニアがN1レベルを取得している必要はなく、担当業務に合わせて日本語能力がどの程度必要なのかを基準とするのがよいでしょう。オフショア開発の場合では、ブリッジSEの日本語能力は重要ですが、オフショア国現地で働くエンジニアには必ずしも日本語スキルは必要とされません。 なお、日本語能力試験の問題は文章読解と聴解のみのため、書く、話す、といった能力は測ることはできません。そのため、ブリッジSEをアサインする際には、面接やディスカッション、メールのやりとりなどを取り入れると良いでしょう。 2. 日本との文化や国民性の違いを認識し、明確に意思表示する 日本と海外では、考え方や仕事の進め方も異なります。日本では、物事をこと細かく伝えなくても相手は当然のごとく察してくれるだろうと期待してしまいがちです。しかし、海外では、相手に明確な意思表示をしなければ伝わらないコミュニケーション文化を持つの国の方が多いです。むしろ、相手に繊細かつ高度な感性を求める日本式コミュニケーションの方がガラパゴス的と言えるかもしれません。 こうした文化や国民性の違いによって意思疎通や相互理解がうまくいかなくなってしまうと、結果として品質低下や手戻りが発生してしまうことがあります。 本側から物事を依頼する時は、目的(なぜやるのか)、スコープ(何をやるのか)、タイム(いつまでに必要か)、コスト(いくら以内でやるのか)を可視化してプロジェクトの目的を一致させ、認識の食い違いを防止することが大切です。 また、開発先の文化や国民性を理解しておくと、誤解や思い違いを少なくできます。時にはやり方を日本式に合わせてもらうように強制するばかりではなく、お互いに文化が違う国であることを理解し歩み寄る姿勢も大切です。 3. 情報共有や取り決めは、可能な限り文書化する 日本では、話し手と聞き手の間に共有されていることが多いため、行間を読み、暗黙的なコミュニケーションが成立しやすい文化といえます。また、日本では会議の場での共有や明確化をすることが多くなりますが、口頭による伝達や暗黙知の共有が含まれるため文書化しにくかったり、伝達する内容が多く労力がかかるという理由から、文書化しないケースが度々見られます。 一方、海外では、共有する情報や経験が少ないため、文章や図解、数値などによって、誰が見ても理解できるような形式で客観的に表現された形式知によるコミュニケーションが行われること多々あります。これは、個人主義的な文化の国ほど強くなえる傾向が見られます。そのため、母国語が異なる国のメンバーと日本語で業務を進めるオフショアの場合には、仕様等を確実に文書化してデータベースで共有するのが望ましいでしょう。 過去にオフショアで失敗を経験した日本企業による教育指導的な役割によって、日本企業とのプロジェクト経験が多いオフショア開発会社ほどそのような体制が整っています。こうした取り組みは、転職率の高いオフショア開発の課題をカバーするためにも有効です。 また、口約束で決まったと思っていたことが後になって変更となり、問題になることがあります。決めごとは合意と承認があって成立するものですので、可能な限り文書化して相互に承認ルールを確認し徹底することが大切です。 4. 仕様変更と品質レベルに関する考え方の違いを意識する 日本では、度重なる仕様変更が生じても、それに対応することが当然であると考えられがちです。一方、オフショア開発では、契約締結後に仕様変更を行うことは一般的とは言えません。そのため、仕様変更を巡ってはトラブルが発生する可能性があります。 […]


28/02/2023

3 minutes
日本企業が抱えるシステム開発の課題と今後のオフショア開発の方向性とは
日本企業のシステム開発は、IT人材不足と開発コスト増加が大きな問題となっています。急速なデジタル化とテクノロジーの進化に追いつくための、適切なITエンジニアやデジタル専門家の確保が難しく、開発コストも上昇しています。この課題に対し、「リスキリング」と「オフショア開発」という解決策が注目されています。企業は、内部のスキル向上とグローバル競争への対応を目指し、オフショア開発を 人材戦略に活用することで、人材不足を克服し、競争力を高める展望が期待されています。 オフショア開発の現状 DX人材不足の解決策としても注目されている、オフショア開発の現状を紹介します。 オフショア開発の規模が拡大している 経済産業省が2019年に発表した「IT人材育成の状況等について」によると、日本では2030年までに約59万人のIT人材が不足すると予想しています。今後も優秀なエンジニアを確保するために、オフショア開発を導入する企業の増加が考えられるでしょう。 DX推進やシステム開発の需要拡大により、日本でのオフショア開発の規模は拡大しています。独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)の調べでは、日本のIT企業の約45.6%がオフショア開発を導入している、またはなんらかの形でオフショア開発に関与しているというデータがあります。 【別記事】なぜ日本のIT企業のオフショア開発が活発化してるのか 中小企業の委託元が増加している 海外進出のため費用と手間がかかり、少し前まではオフショア開発を導入しているのは大企業が多い傾向でした。しかし、最近ではグローバル化が進んでいることや、オフショア開発のノウハウが蓄積されたことによって中小企業の委託元が増加しています。 委託先国としてベトナムが人気 オフショア開発の委託先といえば、かつては中国やインドが人気国でした。近年では人件費が安く、優れた人材が豊富で、真面目な国民性などの要因を持ったベトナムが人気を集めています。 オフショア開発の希望委託先国について、オフショア開発.comがまとめたデータ(2020年1月〜12月に「オフショア開発.com」に寄せられた開発相談の希望委託先国別ランキングより)によると、1位がベトナムで、全体に占める割合は52%でした。 【別記事】【2022年最新】オフショア開発の人月単価相場動向、人気のベトナムほか国別比較 日本企業のオフショア開発導入の目的の変化 昨今、日本企業のオフショア開発導入の目的が変化してきています。以前は、コスト削減が主な目的でしたが、企業のデジタル競争力を高めるDX人材不足の対応策や、品質の確保といった目的にシフトしています。 NFT、DeFi、Web3.0、メタバースなどの新しい風潮 スイスのIMDが発表している「世界デジタル競争力ランキング」で日本は2020年に63カ国中27位という結果で、2021年には28位と順位を下げています。日本の順位は年々デジタル競争力を高めている香港や韓国、台湾と比べると対象的な数値となっています。 日本企業のデジタル化が世界各国の企業より遅れている理由の一つに、DX人材不足が挙げられます。そのため日本で不足しているAI、IoT、ブロックチェーンなどの先端技術スキルを持った人材を補うために、オフショア開発導入に向けての動きが増しているのです。さらなる企業のオフショア開発導入の加速に向けた背景にあるのが「NFT」「DeFi」「Web3.0」「メタバース」などの新しい風潮です。 ブロックチェーン技術をベースにして唯一無二の「一点もの」を生み出せるトークンである「NFT」、金融エコシステムの「DeFi」、仮想空間の「メタバース」など、これらはIT業界やテック業界を越えてさまざまな業界で注目を集めています。これらNFT、DeFi、メタバースなどのブロックチェーン技術をベースにした各カテゴリーを包括する位置付けとなるのが「Web3.0」です。 Web3.0は「分散型のWeb」を意味し、巨大IT企業による支配からのデータの解放を目的としています。世界各国がWeb3.0推進への取り組みが進む中、日本の出遅れを防ぐため日本政府が2022年6月に経済財政運営の指針である「骨太の方針」にWeb3.0の環境設備を明記しました。日本のグローバルな競争力を高めるには、Web3.0のブロックチェーン技術は欠かせません。 オフショア開発における今後の方向性 こうしたことを踏まえ、日本企業のオフショア開発導の今後の方向性は次のようなことが考えられます。 オフショアの役割を下流工程から上流工程まで拡大する 実は、オフショア開発の対象業務は、国によって異なります。例えば、米国企業では、上流工程から下流工程まで任せるのが一般的です。米国のユーザー企業は多数のITエンジニアを採用し、社内のIT部門に配置しているため、基本的には自社システムの開発から運用まで内製化するのが主流です。これは、社内技術やノウハウを社外に流出させないためでもあり、日本のように自社のシステム開発を外部のSI企業に全てお任せするということはありません。 オフショア開発などの外部リソースを活用するのは社内でリソース不足が発生した場合です。また、ユーザー企業にとって開発プロジェクトが完了したら終わりということはなく、リリース後にブラッシュアップしていくことを前提として、アジャイル開発でによってサービスインまでの期間を短縮できるのが特徴ですなどので補うというにで、自社のエンジニアのスキルアップにつながっています。これまでの日本企業のオフショア開発では、海外の委託先には下流工程中心にまかせるのが一般的でした。 従来型の形態では、日本のエンジニアの技術スキルが低下する懸念もありつつも、日本企業が海外の企業と同じような導入形態にならないのは、顧客の要件定義が固まらないという課題があったからです。そこで、作業要領も含め日本での開発と同様に、要件定義を明確に行うことで課題の解消につながり、日本企業でも委託先に上流工程までまかせる動きが拡大しています。これにより日本のDX人材強化も期待できるでしょう。 DX領域にシフト 従来、日本企業が海外の委託先にまかせていたのは、基幹システムや既存システムが中心でした。しかしながら、日本企業が変化の激しいビジネス環境の中で優位性を確立するには、デジタル競争力を高めることが急務となっています。DXによる事業改革が不可避となっている昨今、AI、IoTといったDX領域へと業務の委託内容がシフトしています。 ここでDX領域を委託する際に課題に挙がるのが、海外の委託先にDX領域の開発をまかせてしまうため、自社のエンジニアのスキルアップにつながらないことです。課題の解決策として、上流工程、下流工程の分担を明確にしているウォーターフォール開発ではなく、チームを組んで海外のエンジニアと一緒に要件定義、設計、開発、テストといった開発工程を行うアジャイル開発の活用があります。 日本のエンジニアにとっても、海外の優秀なエンジニアと一緒のチームで働くことで、スキルアップにつながることが期待できます。大手のオフショア開発企業や弊社のエンジニアの技術レベルは高く、DX時代にふさわしい優秀な人材を確保することも可能です。 人材不足面でのオフショア開発活用 上記の1、2では日本のDX人材、エンジニアのスキルアップに向けたオフショア開発企業の活用についてお伝えしましたが、日本国内のIT人材不足はいまだ解消されていません。日本におけるDX領域の開発は急務ですが、依然としてレガシーシステムは稼働しており、メンテナンスや運用、開発のための人材が必要です。 しかし、日本のIT人材絶対数の不足もさることながら、日本国内の若いエンジニアにはPythonなどの言語が人気で、レガシーシステムなどに必要なCOBOLなどの昔ながらの言語は不人気という状態です。このような既存システム、基盤システムなどのレガシーシステムにおける人材不足面を解消するためにも、オフショア開発が活用されています。 オフショア開発導入はDX人材不足解消と育成につながる DX時代の人材戦略「リスキリング」の重要性 日本の近年、グローバルな競争が激化する中、日本企業はさまざまな手段を活用して競争力を高めることが求められています。日本のデジタル競争力を高めるためにはDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が叫ばれるものの、国内のITエンジニアやDX人材などの人材不足が大きな課題となっています。 日本のITエンジニアやDX人材不足は、急速なデジタル化やテクノロジーの進展に追いつくことが難しくなっています。このような状況下で、企業は従業員のスキルアップを重視し、最新の技術やトレンドに対応でき、変化するビジネス環境に適応できる人材を育てる必要性があります。こうしたことから、日本のITエンジニアやDX人材不足を解消するため、「リスキリング」が注目されています。 リスキリングとオフショア開発の関係性 オフショア開発は、日本のITエンジニアにとって新たなスキル向上とグローバルな成長の機会を提供する重要な手段となっています。 オフショア開発を活用することで、日本のITエンジニアはグローバルなプロジェクト経験を積むことができます。異なる国や地域の開発チームと協力することで、異文化環境におけるプロジェクト管理やコミュニケーションスキルが向上し、柔軟性や適応力を高めることができるでしょう。 そして、オフショア開発では、リモートコミュニケーションが主要な手段となります。ITエンジニアは遠隔地の開発チームと円滑にコミュニケーションを取るため、効果的なコミュニケーションスキルを磨く必要があります。適切なコミュニケーションにより、要件の理解や問題解決がスムーズに行われ、プロジェクトの成功につなげることができます。 さらに、オフショア開発によって最新の技術トレンドにアクセスする機会が増えます。世界中の開発者と協力してプロジェクトを進めることで、新しい技術や開発手法を学び、実践する機会が増えるでしょう。これにより、ITエンジニアの技術力や知識が向上し、自己成長が促進されることが期待されます。 また、オフショア開発には異なる地域の開発チームと協力することが求められます。これにより、ITエンジニアはチームワークとリーダーシップのスキルを発展させる機会を得ます。プロジェクトの成功に向けて指導力を発揮し、チームと協力して目標を達成する経験を積むことで、エンジニアとしての成長が促進されるでしょう。 こうしたことから、オフショア開発の経験は、日本のITエンジニアのスキルアップとグローバルな視点の向上に寄与すると言えます。グローバルなプロジェクト経験、コミュニケーションスキルの向上、最新技術の習得、チームワークとリーダーシップの発展といった点に着目することで、オフショア開発がエンジニアのキャリアにプラスの影響を与えることが期待されます。 オフショア開発とリスキリングの組み合わせは、企業のデジタル化戦略を推進する上で有益なシナジーを生み出すことが期待できます。 無料eBookのダウンロード 保存版 オフショア開発入門ガイド2023 オフショア開発を始める前の気になる疑問を解決!オフショア開発を検討中の方に向けて、オフショア開発の基本的な知識から注意点までを解説します。 今すぐダウンロード(無料)


31/01/2023

3 minutes
ラボ型開発(ラボ契約・ODC)とは?請負契約との違いメリット・デメリット
アプリケーションなどのソフトウェアを開発するにあたり、自社内で開発する内製と、自社以外の企業に開発を依頼する外製の2つの開発初方法があります。 内製では、自社の技術開発力の向上につながるというメリットがある反面、専門知識を保有する技術力の高い社員のエンジニアの存在が不可欠であり、またプロジェクトの遅延やシステム完成後もエンジニアの維持確保が必要になるというデメリットもあります。そのため、専門性の高い部分を全て外部に委託することができ、プロジェクトの遅延も発生しにくい外製によるソフトウェア開発を行う企業が多くあります。 昨今では、そうした開発リソースを、国外の外国人エンジニアの活用によって確保するオフショア開発が盛んに行われています。今回は、オフショア開発のなかでもラボ型開発と呼ばれる形態について、その概要やメリット・デメリット、ラボ型開発に向いている案件について解説します。 ラボ型開発(ラボ契約・ODC)とは ラボ型開発とは、海外のリソースや企業を活用して開発する「オフショア開発」の一種で、「ラボ契約」「オフショア開発センター(ODC)」と呼ばれることもあります。ラボ型開発はオフショア開発における契約形態のひとつで、近年は請負契約よりもラボ型開発を含む準委任契約が多い傾向にあります。 請負契約 仕事の完成までを請け負う契約。発注者は要件を明確に定義し、ベンダーは作成された仕様書に沿って設計・開発から実装・テストまでを行い、期日までに成果物を納めるというもの。 準委任契約 特定の業務を遂行することを定めた契約。請負契約とは異なり、成果物の完成の有無は問わない。準委任契約は、さらにラボ契約とSES契約に分けられる。 SES契約 エンジニアを発注元に常駐させる。ラボ型開発同様、エンジニアチームを組んでプロジェクトを進めていく。より流動的な案件や、エンジニアを教育したい場合などに用いられる。 B-O-T方式 現地オフショア会社が人材リソースを確保し安定運用後にチームを丸ごと買い取る方式。Build(設立)、Operate(運営)、Transfer(委譲)を略した言葉。 請負契約では、ベンダーが納品した成果物に対して報酬が支払われます。一方で準委任契約ではベンダーが行う労働そのものに対して報酬が支払われるため、請負契約とは異なりプロジェクトの内容や進捗状況に応じて柔軟な変更が可能です。 近年では、ラボ契約とSES契約の両方を活用する「ハイブリッド型」の契約形態をとることも多く見られます。例えば、プロジェクトのキックオフから1〜2ヵ月間はSES契約で業務に慣れてもらい、その後帰国してラボ契約で働いてもらったり、人数を減らしたりするといったケースです。 オフショア開発について、詳しくは以下の記事で紹介しています。 【別記事】オフショア開発とは|メリット・デメリット・成功に導く6つのポイント ラボ型開発と準委任契約の違い ラボ型開発(ラボ契約)は準委任契約の形態のひとつです。システム開発における委託契約は前述の「請負契約」または「準委任契約」によってなされますが、請負契約が成果物の完成を目的とするのに対し、準委任契約は労働の代行を目的としている点が異なります。単純に「準委任契約」と言う場合はシステム開発以外にも使われ、準委任契約のなかのシステム開発における形態がラボ型開発ということになります。 ラボ型開発(ラボ契約・ODC)のメリット ラボ型開発には、以下のようなメリットがあります。 一定期間、専属開発チームとしてメンバー固定でエンジニアを確保できる ラボ型開発では期間を決めて契約するため、期間内であれば継続的に案件の発注が可能です。期間内にいくつか連続して案件が入る場合でも、案件ごとにチームを組み直したり、一から情報共有をしたりする手間が省けます。 近年、東南アジア諸国のエンジニアは日本国内のエンジニアと遜色ないか、よりハイスキルなことも少なくないため、優秀な人材を中~長期間にわたり確保できます。 中~長期間腰を据えて案件に取り組むことで、ラボ型開発の委託先が発注側の業務体制や企業風土に慣れることができ、安定的に開発できるのも大きなメリットです。優秀な人材リソースを安定的に確保して開発できれば、機能を拡張しバグを改修する作業や業務を進めるための時間的リソースも確保しやすくなります。それにより、エンジニアも高いクオリティの成果物をスピーディーに納品することが可能になります。 自社内に開発経験やノウハウを蓄積できる ラボ型開発では、同じエンジニアメンバーと一定期間協働するため、自社内に開発ノウハウが蓄積しやすいのも大きなメリットです。ノウハウが蓄積できれば、別の案件でも開発スピードが改善されたり、チーム間で円滑なコミュニケーションがとれたりと、さまざまな良い影響が考えられます。ノウハウ蓄積も目的に組み込む場合、その分野に特化した企業とラボ型開発を行うのもひとつの方法です。 要件がはっきり定まっていないプロジェクトでも取り組むことができる ラボ型開発では、請負契約と異なり成果物が明確に決まっているとは限らず、途中で仕様変更をしたり、各種調整したりすることも容易です。企画や施策が確定していない状態でも、協働しながら進めていけるでしょう。請負契約のように、仕様変更や調整について追加費用が発生することもなく、契約期間内なら自由にリソースを使えます。 例えば、ラボ型契約で5名のエンジニアに開発を依頼した場合、最初の4カ月は全員に新規のアプリケーション開発を依頼し、その後の2カ月は3名が追加機能の実装を担当し、2人に細かいバグ対応や改善を担当するなど、フェーズや状況に応じて臨機応変かつ柔軟にチームを動かすことができます。 ラボ型開発(ラボ契約・ODC)のデメリット ラボ型開発には、以下のようなデメリットがあります。 開発チームの立ち上げや維持にコストがかかる ラボ型開発は一定期間専属のチームを確保できる契約なので、一定量の発注を続けられる場合はコストパフォーマンスが良いです。一方、契約期間内はコストが発生し続けるため、依頼する案件の業務や作業量が極端に少ない場合に予定よりも早く開発が完了しても、その後に依頼する案件がない期間があるとその分は余計なコストとなり、請負契約よりもコストが高くなってしまう可能性があります。特に、単発の案件や短期の案件の場合は割高になってしまう可能性があり、チームを中長期に渡って押さえておくメリットが得られにくいでしょう。 契約期間中は人材リソースを無駄にしないように、一定の業務量を発注できる準備を行っておくとよいでしょう。少なくとも3カ月以上の開発が必要となる案件か、複数の単発・短期の案件を準備しておき、リソースを余らせないようにするのがおすすめです。 発注者が主体的にマネジメントする必要がある 開発をスムーズに進めるためには、チーム構築のほかに体制作りが必要です。特に、ラボ型開発では請負契約のようにすべてを発注先に任せられるわけではなく、チームとして協働する形態となるので、コミュニケーションが特に重要になります。このように、発注元が主体的にチームビルディングやマネジメントをする必要があることから、発注元の負担は請負契約と比べると大きくなります。 特にオフショア開発では、日本語が堪能な委託先に依頼できるとは限りません。国内に日本法人や支社があるオフショア開発会社を選んだり、開発技術だけでなくコミュニケーション言語の能力も含めて人選したりして、コミュニケーションに齟齬(そご)が生まれないような体制作りが必要です。 チームビルディングに時間がかかる ラボ型開発では、初めにチームを構築します。チームメンバーを選ぶ際には、単純にスキルが高い人材を集めればよいとは限らず、開発内容や自社の文化などさまざまな要素を考慮し、開発内容に合っていて相性の良い人材を慎重に選んでチームを構築する必要があります。 また、チーム構築から実際に開発に入るまでは一般的に半月~3カ月程度の期間が必要なため、その期間も考慮しなくてはなりません。 また、ラボ型開発では、発注元がチームの一員となって開発を指示する必要があります。成果物の仕様にズレが生じないようチェックしたり、メンバーに体制や企業風土についてレクチャーしたりすることもあるでしょう。チーム結成後の滑り出しがうまくいくとは限らず、チームとしての機能が軌道に乗るまではある程度時間がかかることを念頭に置きましょう。 ラボ型開発(ラボ契約・ODC)が向いている案件 ラボ型開発は、以下のような案件に向いています。 定期的に発生する案件がある 業務委託したい案件が定期的に発生するのであれば、ラボ型開発がおすすめです。特に、既存のアプリやサービスの運用・改修をする場合に向いているでしょう。契約期間中は自社専属の開発チームを確保でき、案件が変わるごとにチームを再構築したり、一から情報共有したりする必要がありません。 そのため、開発案件が途切れず発生するけれど人員が足りないという場合にラボ型開発を利用すれば、案件ごとに依頼先を探したりすり合わせをしたりする手間がかからず、コストやストレスの軽減につながるでしょう。 仕様変更や修正が生じる可能性がある ラボ型開発は契約期間内であれば追加費用なしで対応してもらえるので、完成形がはっきり決まっていない案件や、仕様の追加や変更が生じやすい案件に向いています。請負型に比べてコストが抑えられるだけでなく、中~長期にわたって同じチームで作業していくので、指示を的確に理解して適切に作業してもらいやすいでしょう。 また、AI等の先端技術を用いたIT開発や、完成形が定まりにくい研究開発の要素を含むという場合にもラボ型開発は向いています。 アジャイル型開発の案件である システムやアプリの開発には、大きく分けてウォーターフォール型とアジャイル型の2つの開発体制があります。 ウォーターフォール型 開発の最初の段階で要件や仕様を詳しく決定し、すべて完成してからリリースする。 アジャイル型 […]


23/12/2022

3 minutes
ノーコード開発で何ができる?どんな用途に向いているのか理解しよう
ノーコード開発は、今注目されている開発手法です。ノーコードツールを使えば、高い専門知識を持つIT人材でなくてもアプリケーションやWebサイトを開発でき、コストも開発期間も抑えられます。IT人材の不足が大きな問題になっているなかで、新たにIT人材を雇用したり育成したりしなくてよいのは大きなメリットです。 しかし、ノーコード開発はコーディングしないため拡張性や汎用性が低く、できることには限界があります。今回はノーコード開発の概要と、できることとできないことを説明します。 ノーコード開発とは ノーコード開発とは、コーディングせずにシステムやサービスを開発すること、またはその開発環境のことです。開発環境はノーコードツールとも呼ばれます。コーディングは一般的にプログラミングとも呼ばれるもので、プログラミング言語を用いてプログラムを書くことです。 ノーコード開発ではコーディングが不要なので、高度なスキルや知識がない、非IT人材でも開発できます。そのため、ユーザーが現場で必要なアプリケーションを開発でき、現場のニーズに合わせた開発が可能です。システム開発の担当者との打ち合わせも不要なので、開発時間を短縮できます。 そのため、ノーコード開発はIT人材不足を補い、デジタイゼーションを進め、DXを推進する方法のひとつとして期待されているのです。 ノーコード開発では、コーディングの代わりにツール上で用意されたコンポーネントと呼ばれる部品を組み合わせて開発します。コンポーネントを使うため、必要なものを素早く開発することが可能です。 ただし、コンポーネントのないものは作れないので、自由度は低く、オリジナル部分の多い開発や大規模開発には向きません。また、コーディングの余地がないため、カスタマイズや拡張も不得意です。 ローコード開発との違い ノーコード開発と似たものに、ローコード開発があります。ローコード開発とは、ほとんどの部分をノーコードで開発できるものの最小限のコーディングが必要な開発手法や、その開発環境のことです。コーディングするため、ノーコード開発よりも高い汎用性や拡張性があります。 一方でノーコード開発はソースコードの記述をせずに開発でき、開発に高いスキルは不要です。ただし、コードが使えないため、細かな部分での修正や調整ができません。また、ノーコード開発は開発ツールによってできることが変わります。 従来のように「すべての部分をコーディングで作成する」場合はフルコード開発と言います。最も難易度が高く、専門的なスキルが必要ですが、自由度や拡張性も高い方法です。 ローコード開発や、IT人材不足との関係については、次の記事を参考にしてください。 「ローコード開発とは? IT人材不足解消の切り札として注目される新しい手法」 ノーコード開発、ローコード開発、フルコード開発の違い ノーコード開発 ローコード開発 フルコード開発 コーディング 不要 少し必要 必要 スキル 高いスキルは不要 高いスキルは不要だが、ある程度のスキルは必要 高いスキルが必要 拡張性、自由度 低い コーディングにより確保可能 高い拡張性と自由度がある 開発期間 短い 短い 長い ノーコード開発が向いている場合 ノーコード開発は次のような場合に向いています。 スモールビジネスを行う個人である場合ネットショップ運営やアプリ制作などのスモールビジネスに使えます。また、ほかの業種でも、スモールビジネスを行う個人が必要なアプリケーションを制作することも可能です。 小規模なソフトウェアベンダーである場合小規模アプリの開発を行うベンダーで開発環境として使えます。 スタートアップ・ベンチャーである場合開発期間を短縮し、効率的に事業を始められます。 部署内で小さなアプリケーションが必要な場合情報システム部門に頼らず、短期間で欲しいアプリケーションを制作できます。その他、開発コストを抑え、短期間でサービスをリリースしたい場合に向いています。 ノーコード開発でできることとできないこと その性質上、ノーコード開発にはできないことがあります。特徴と限界を理解して使いましょう。 ノーコード開発でできること Webページ制作企業・団体のWebサイト、商品のサービスサイト、ECサイトなど。 Webアプリ制作フロントエンド、バックエンド、データベースといったWebベースのアプリケーション。 業務の自動化・効率化のための小さなアプリケーション制作日常的な業務を効率化する小規模なアプリ、単機能に特化したアプリ、データ管理アプリなど。 モバイルアプリ制作業務に利用するスマートフォンアプリ。 ノーコード開発でできないこと ノーコード開発では、次のようなシステム開発はできません。 大規模で複雑なシステム開発拡張性や自由度が低いので、複雑なシステム開発には向いていません。 独自部分の多いシステム開発ツールに装備されているコンポーネントを使って開発するため、独自部分の多い開発はできません。 ツールの対象となっていない分野の開発ノーコードツールにはそれぞれ対象とする分野があります。 ゲームのように表示速度が重要なシステムの開発ノーコードで開発した場合、ページの読み込み速度が遅くなる傾向にあります。 […]


15/12/2022

3 minutes
ローコード開発とはIT人材不足解消の切り札として注目される新しい手法
ローコード開発は、基本的にはコンポーネントの組み合わせですが、ある程度のコーディングが可能な開発手法です。ノーコード開発とは異なりコーディングできるため、外部との連携といった拡張性や自由度もあります。ただし、ツールによってできることには制限があります。


24/11/2022

3 minutes
Salesforceのカスタマイズや開発を行うにはオフショア開発が安心
Salesforceは、自社に合わせてカスタマイズして導入する必要があります。また、Salesforceを利用してシステムやアプリを開発することも可能です。カスタマイズやシステム開発にはスキルやノウハウが必要なので、ベンダーを利用したオフショア開発をおすすめします。


12/10/2022

3 minutes
【2022年最新】オフショア開発の人月単価相場動向、人気のベトナムほか国別比較
オフショア開発で最適な国を決定するときには、コスト、言語、文化、時差(タイムゾーン)、信頼性など考慮すべき要素がいくつかあります。詳しくは『オフショア開発とは|メリット・デメリット・成功に導く6つのポイント』でも紹介していますのでご覧ください。本記事では、オフショア開発に最適な国を知る上で重要となる、各国の人月単価と国ごとの特徴について紹介します。 オフショア開発国のITエンジニアの人月単価相場 ITエンジニアにかかるひと月あたりの人件費を人月単価と言います。人月単価は、コスト削減を目的としたオフショア開発で最適な国を決定する際の1つの尺度となります。昨今の日本国内のITエンジニアの平均人月単価の相場が80~100万円前後と言われています。 それでは、オフショア開発委託先の国の人月単価相場はどの程度低いのでしょうか。人月単価相場は、それぞれの国の物価や人件費、ITエンジニアの技術力の差などによって異なります。以下の表は、株式会社Resorz(オフショア開発.com)が発表した『オフショア開発白書 2022年版』によるオフショア開発委託先の国のITエンジニアの人月単価相場を元に当社が作成したものです。 日本企業のオフショア開発の聡明期から委託先として主流だった中国とインドは、他国に比べて人月単価相場が高めになっています。また、中国とインドのブリッジSEの相場が昨年から高騰しており、日本との人件費の差がかなり縮まって相場的にはコスト削減効果は薄れています。なお、最新の北京や上海のSEの人月単価は下記の表よりも大幅に値上昇して「日中逆転現象」も発生しています。 一方、ベトナム、バングラディッシュ、ミャンマーなどの東南アジアの国々の相場は、日本の相場と比較してもまだ魅力的な人月単価相場となっています。 特に、ベトナムは、ITエンジニアのレベルが高い人材が多い上に、人月単価相場は急騰することもなく安定的に推移しており大変魅力的な国となっています。 また、バングラディッシュでは、PG、SE、ブリッジSEの相場が急騰しており、今後が気になるところです。 ITエンジニアの人月単価相場は、必要とされるリソースの需要と供給のバランスによって左右されるほか、各国の経済状況や雇用状況、為替変動などの影響により変動します。円安・円高などの為替変動によるリスクを回避するために、円建ての取引きやその他の為替リスクヘッジ対策を行うことも重要です。 オフショア開発で人気の各国の特徴と国内事情 ベトナム ベトナムは、日本のIT企業に人気No.1のオフショア開発国です。ベトナムは古くから日本が政府開発援助(ODA)などで支援をしていたこともあり、親日派が多いことで知られています。また日本の電機メーカーや自動車メーカーや二輪メーカーが多く進出しており、身近に日本を想起させるものが多いことも日本への親近感を強くしている理由です。 ベトナムは社会主義国ですが、安定した政治と高い経済成長率を保っています。柔軟で慎重な金融政策により、消費者物価指数は年率4%未満を維持しており、世界でも急速に経済成長を遂げている国のひとつです。 IT政策の面では約300の大学と専門学校でICTトレーニングを提供し、ICT履修生徒数は約55,000人を数えるなど、インダストリー4.0向けのデジタル人材を国家戦略として積極的に育成しています。充実したICT教育により、高度なスキルとモチベーションの高い豊富なIT人材プールを保有しています。IT人月単価は中国、インドよりも安く、バングラデシュ、ミャンマーよりはやや高めです。 中国 オフショア開発の黎明期に人気No.1だったのが中国です。中国は文化大革命後に驚異的な経済発展を遂げ、今やGDPでは日本を抜き世界第2位となりました。政情は中国共産党一党独裁であり、国の事情に応じて規制がすぐ変化するのが難点と言えます。これをカントリーリスクと捉え、中国から撤退する外国企業や日本企業も近年は多くなっています。 中国は人口が多く、IT人材も豊富で高度な技術力を持つ優秀なITエンジニアがいることが特徴です。一方、人月単価は相対的に高騰しており、直近では日米逆転現象も起こっているケースが見られます。また、転職を繰り返すジョブホッパーが多いので、人材の入れ替わりが激しいことは覚悟しておく必要があります。 インド インドは中国と並び、昔からオフショア開発が盛んな国です。中国と同様に人口が多くIT人材も豊富で、高度な技術力を持つ優秀なITエンジニアがいることが特徴です。なお、未だにカースト制度の影響が残っているため高度な教育を受けられる人は限られています。 日本とは友好関係にあり、円借款によりインド国内では上下水道の整備や鉄道の拡充などが行われています。インドのオフショア開発は欧米企業との取引が多く、コミュニケーションは英語が中心です。IT人月単価は相対的に高めです。 フィリピン フィリピンもオフショア開発では人気の高い国です。フィリピンには、以前から日本が積極的に経済援助しているため両国の関係は良好です。日本企業も多く進出しており、ソフトウェアを中心としたIT人材も比較的多いと言えるでしょう。 ただし、フィリピンは近年こそ政情的に安定はしていますが、治安には問題があります。犯罪率は年々減少しているものの、強盗や殺人などの重大犯罪が多く、赴任や出張などの際にはセキュリティに注意が必要です。コミュニケーションは英語が中心です。IT人月単価はベトナムと同程度で、バングラデシュやミャンマーよりもやや高めです。 バングラデシュ 人件費によるメリットと年21%のICT市場の年間平均成長率(バングラデシュICT省2019資料より)を背景に、近年ポストベトナムと呼ばれるほど注目を集めてたのがバングラデシュです。バングラデシュは全方位外交を進める国であり、近隣のインドをはじめ、中国、アメリカ、日本などと友好関係にあります。 日本からは政府開発援助として資金提供しており、運輸や電力などのインフラ整備を積極的に行っています。しかし、原材料・部品の現地調達の難しさや通関に時間を要すること、電力不足・停電、従業員の賃金上昇など、まだ不安定な要素が多いことが課題となっています。 国としてはIT立国を目指しており、教育投資の結果、近年はIT人材が急増しています。人月単価はベトナムやフィリピンより安く、ミャンマーより若干高い水準。ただしインターネット環境など、ITのインフラ整備がまだ追いついていなかったり、電力需要が日々増加しており電力需要が発電能力を常に超えているため、しばしば停電を強いられることなどが難点となっています。 ミャンマー 以前から日本はミャンマーに対して多額の政府開発援助を行っており、日本との関係が深い国です。IT系大学のトップレベルの優秀なIT人材でも買い手市場と言われ、人月単価もバングラデシュより若干低い水準で「アジア最後のフロンティア」などと呼ばれて注目を集めた時期もありました。しかし、まだまだ発展途上のためにITインフラが整っておらず、輩出する人材数はそれほど多くなく技術レベルにも差があります。 2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生して1年以上を経過しましたが、現在もなお同国は揺れている状態です。これまでに国軍の弾圧により多くの民間人の死者や拘束者が出ており、2022年になった現在も増加しています。クーデターに加えてコロナの影響も加わり経済状況は悪化しています。このような状況下において、進出している日系企業のビジネスへの影響が懸念されています。 オフショア開発委託先の選定は総合的に判断 コスト削減を目的としたオフショア開発では、ITエンジニアの人月単価だけに注目することは危険です。オフショア開発国を選定する際には、優秀な人材やスキルの供給源として長期的な視点で関係性を築いていくことも大切なことです。そういった視点を加味したうえで、IT人材が豊富であることや、人月単価、政情や治安など総合的にバランスがとれているベトナムに人気が集中している点はうなずけます。 また、何よりオフショア開発のプロジェクトを円滑に進められなければ、オーバヘッドにより人件費オーバーになってしまう危険性もあります。オフショア開発の委託先となるパートナーが信頼関係を築くことができる相手なのか、優秀なIT人材が確保できるのか、自社の開発プロセスで必要な工程をアウトソーシングできるのか、言語やコミュニケーションの壁をどのように乗り越えられるのかなど、日本企業とのビジネスが円滑にできるかどうか、実績や経験も踏まえて総合的にチェックしておきましょう。 無料eBookのダウンロード 保存版 オフショア開発入門ガイド2023 オフショア開発を始める前の気になる疑問を解決!オフショア開発を検討中の方に向けて、オフショア開発の基本的な知識から注意点までを解説します。 今すぐダウンロード(無料) 無料eBookのダウンロード チェックリストでわかる 失敗しないオフショア開発会社の選び方 オフショア開発会社選びの準備から開発開始まで、多様な角度からチェックポイントを網羅。チェックリストを活用して効率的な選定や基準作りに役立ちます。 今すぐダウンロード(無料)


12/10/2022

3 minutes
オフショア開発とは|メリット・デメリット・成功に導く6つのポイント
日本国内のIT人材不足が深刻化する昨今、オフショア開発は人材リソースを確保できる限りではなくさまざまなメリットをもたらします。本記事では、オフショア開発のメリット・意思決定や開発プロジェクトを成功に導くポイントについて解説します。 オフショア開発とは オフショア開発とは、ソフトウェア開発やWebシステム開発、システムの保守運用などを、海外のシステム開発ベンダーや海外現地法人などにアウトソーシングすることを言います。 日本のIT企業におけるオフショア開発の目的は企業ごとのそれぞれの、主な目的としては、「開発コストの削減」「エンジニアの適正化」「現地市場への参入」と言えます。 開発コストの削減 システム開発費用の大半を占めるものは人件費です。そのため、東南アジアや南アジアなどの賃金が低い海外エンジニアを活用して人件費を抑えることで開発コストを削減することができます。どれ程度のコストが削減できるかは、オフショア開発委任国をどの国にするか、どの工程のどんな内容を対象とするかなどにより、削減できる費用は異なります。 エンジニアの確保 日本国内ではエンジニア不足が続いており、今後は更に深刻化する見通しで大きな課題となっています。一方、オフショア開発の委託先となる国々では、IT産業が著しい成長を遂げています。これは、国や政府主導でITエンジニアの育成に取り組んでいる結果であり、若く優秀な人材が豊富です。また、それぞれの国に日本や英語などの外国語教育にも力を入れている企業もあり、日本企業の受け入れ体制を整えています。そのため、日本企業にとっては人材リソースを確保しやすく、必要なリソースを必要なタイミングで活用できるようになっています。 現地市場へ参入 中国や東南アジアの国々の現地市場に自社の製品を投入するために、現地進出してローカライズや保守などをオフショア開発でを行う日本企業が増えています。 オフショア開発のメリット 開発コストを削減できる まずは、開発人件費の削減があげられます。オフショア開発委託国の選び方次第で差はありますが、オフショア開発の黎明期に比べるとアジア圏の人件費(人月単価)は全体的に上昇傾向にあります。しかし、それでも東南アジアや南アジアのITエンジニアの人件費は日本よりも安価なレベルで維持されています。人件費は開発コストの中で最も大きな割合を占めるため、開発規模が大きな案件や開発期間が長い案件ほどコスト削減のメリットは大きくなります。 必要な人材だけを確保することができる 開発に必要な特定スキルを持つ人材を確保することができます。人材が確保できないことによって開発がスタートできない、遅れる、もしくは開発費が高騰してしまう、といったことなくプロジェクトを進められます。 開発プロセスの必要な工程をアウトソーシングできる 開発工程の一部をアウトソーシングすることができます。例えば、開発プロセスでボリュームが大きくコストがかかる工程を切り分けてアウトソーシングすることで、大幅なコストダウンやスピードアップを図ることができます。 また、一部の有力なオフショア開発企業においては、日本企業との豊富な取引経験や実績を有し、企業規模も大きくITエンジニア数を数千人規模にまで拡大している企業も存在しています。そのようなオフショア開発企業には経験豊富で優秀な人材が大量に集まっており、上流工程から下流工程までの一貫した開発プロセスに対応できる体制を整えています。 国内で不足している先端IT技術者を確保できる 例えば、ベトナムでは、自国における第4次産業革命に対応する研究開発や応用技術の活用を国家として推進しており、自国の内でソフトウェア開発業務を行うオフショア開発会社を支援しているため、先端IT技術者を育成する土壌があります。 そうしたことから、オフショア開発国には世界的な潮流に敏感で、先端技術分野においても前向きに取り組む若くて優秀なエリート人材が多く、DX推進に不可欠な先端IT技術者を確保することが可能です。 実際に、先端技術に積極的に取り組むオフショア開発会社では、自国政府や公共機関向けに、先端デジタル技術を活用した自動化システムや自立制御システムなどの様々な先端システムを開発した実績を持っており、高い技術力を幅広く保有していると言えます。 開発形態、契約形態を選ぶことができる オフショア開発における主な契約体系としては、請負型開発(請負契約)とラボ型開発(準委任契約)があります。 【請負型開発(請負契約)】 請負型開発は、発注側の仕様や要件に基づいて開発を行い納期までに成果物を納品する契約で、納品される成果物に対して対価が発生します。したがって、発注側は開発プロセスにあまり関与しません。また、オフショア開発会社側は瑕疵担保責任を負います。 請負型開発では、主にウォーターフォール型で開発を進めていきます。事前にシステムの仕様や要件を詳細に定めて、要件定義から運用までの一連の工程を上流から下流まで順番に進めていく手法のため、途中での仕様変更は困難になります。そのため、事前に要件が固まっていて変更の可能性がないことや大規模開発などに適した方法になります。 【ラボ型開発(準委任契約)】 ラボ型開発は、発注側の要望にマッチしたスキルを持ったオフショア開発会社の開発要員が一定の期間、発注側の専属要員として開発を行うというもので、労働期間に対する契約となります。通常は、一定期間(3ヶ月、半年、1年など)ごとに見直すことができます。費用は、一般的には各開発要員のスキルや経験、業務量等に応じて人月単価が設定されており、毎月必要な業務に従事する要員数と人月単価の積で計算されます。 契約期間中は、自社専属の開発チームとして業務に取組むため、開発人員を一定期間内確保できるとともに、社内に開発ノウハウを蓄積することができるメリットがあります。なお、労働期間に対する契約のため、オフショア開発会社側には成果物に対する瑕疵担保責任はありません。 ラボ型開発では、ウォーターフォール型で開発を進めることもありますが、アジャイル型で進めるケースも多くなります。アジャイル開発では、要件定義から運用までの一連の工程を順番に行うのではなく、短期間に小さな開発規模で分析・設計、開発、テスト、リリースを行い、その一連のサイクルを何度も繰り返し実施します。 そのため、小~中規模の開発に適しており、要件や仕様の詳細が定まっていない場合にシステムの開発を進めながら詳細な仕様を詰めていったり、市場や顧客の動向を見ながら機能の修正や変更を行ったりといった柔軟な対応が可能になります。また、サービスを短期間で素早くローンチしたい場合などにも有効です。 【BOT方式(Build – Operate-Transfer)】 その他にも、近年はラボ契約の進化形とも言える「BOT方式(Build – Operate-Transfer)」も注目されています。BOT方式とは、自社のオフショア拠点の設立する上で、まずは現地オフショア開発会社に自社専用のオフショア開発センター(ODC:Offshore Development Center)を作って開発、運用を進め、それが安定的に稼働できることを確認した後など、一定の条件のもとでODCを買い取って子会社化する契約方式です。 現地法人設立初期コストを押さえつつ、現地開発拠点の構築(Build)、運営(Operate)、委譲(Transfer)まで、ローリスクかつスピーディーに実現可能です。 オフショア開発における課題 言語の壁 オフショア開発を委託する場合に一番気になることは、言葉の壁でしょう。言葉の壁によりコミュニケーションロスが生じて開発に支障が出る可能性があるからです。実際にはどこの国にオフショア開発を委託しても主言語は英語になることがほとんどですが、日本企業向けのオフショア開発企業であれば日本語スキルが高い人材が在籍してるので、必要に応じてそうしたブリッジエンジニアを採用すれば問題は解消できます。 文化や商習慣の違い 文化(国民の祝日や旧正月)や商習慣(定時で帰る、残業はしない、休日出勤はしない)の違いにより、開発スケジュールに支障が出る可能性があります。ただし、あらかじめ現地の開発リーダーやブリッジエンジニアを採用していれば、休みなどは事前に予測でき開発メンバーに残業の交渉もしてもらえるため、あまり問題にはならないでしょう。 海外との時差 海外との時差がミーティングの支障になる場合もあるでしょう。ただし東南アジアであれば時差は1〜2時間なので、オンラインミーティングやチャットなどの、コミュニケーション手段を活用すれば問題は解消できることがほとんどです。ただし物理的にモノ(契約書、サンプル等)を届けたりする場合は、1週間程度時間を見る必要があります。 品質やセキュリティに対する意識の差 国民性が影響し、品質やセキュリティに対する意識が異なる場合があります。一般的にはテストや評価の基準を明確(書面)にし、事前にセキュリティ教育を行うなどして対処しますが、経験豊富なオフショア開発企業に委託すれば、情報セキュリティ対策や品質マネジメントシステムを導入しているので安心できるでしょう。 オフショア開発を成功に導く6つのポイント オフショア開発の課題には、コミュニケーションや文化の違いに関すること以外にも、仕様書の問題、分業分散体制への取組み、オフショア側を見下したり丸投げして管理不在になる問題など、日本側の姿勢に起因するものも含まれます。 そうした課題を克服し、オフショア開発を成功させる主なポイントをご紹介します。 文化や習慣の違いを埋める まずは、オフショア拠点を置く国のカントリーリスク、文化や商習慣、国⺠性の違い […]


12/10/2022

3 minutes
なぜ日本のIT企業のオフショア開発が活発化してるのか
現在、日本のIT企業では、IT人材不足と労働生産性の問題が深刻化しています。このような状況の中、エンジニアの不足解消とIT人材の適正を目的として、多くの企業が導入しているのがオフショア開発です。本記事では日本のIT企業におけるオフショア開発導入の経緯と潮流について解説します。 日本のIT企業におけるオフショア開発の経緯 日本のIT企業によるオフショア開発は1980年代から始まりました。2000年代になるとオフショア開発の市場規模は急速に拡大し、2008年には1000億円規模に到達しました。総務省の統計によると、2007年の時点で、日本のソフトウェア開発企業の36.8%がオフショア開発を活用しています。 基幹システム開発における一般的な開発手法はウォーターフォール型で、その開発プロセスのうち開発コスト費用が最も多くかかるのは、上流工程以後のコーディングや単体テストといった下流工程です。この工程は、工数は膨大であるものの付加価値として低いと考えられたため、開発プロセスを分業化して単価の安い下請け企業にアウトソーシングすることで開発費を大幅削減しようという取り組みが広がりました。 こうした開発の分業体制とアウトソーシング化は、元請けから下請け、ニアショアへと再委託が進み、さらにより安い単価を求めて中国などの海外のソフトウェア開発企業の活用が増加したことにより、オフショア開発による国際分業体制が確立されていきました。 2000年代後半に入ると、オフショア開発国として先行していた中国における人件費の高騰や、中国国内の政治、経済、社会情勢などの変化に起因するリスク、いわゆるカントリーリスクが懸念材料とされ、日本企業はオフショア開発を中国からベトナム、フィリピン、インド、などへのシフトを進めました。 このような経緯から、現在は東南アジアや南アジアは優良なオフショア開発国と認識されるようになっており、中でもベトナムは日本企業に最も人気のあるオフショア開発国となっています。 日本企業が抱えるIT人材不足とレガシーシステムの問題 現在、日本国内のIT産業は深刻な人材不足の危機に直面しています。2018年に経済産業省が発表した『DXレポート』によると、2025年には日本国内で43万人ものIT人材が不足すると予測されています。 さらにこの中では、日本企業の将来の成長および競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネス・モデルを創出・柔軟に改変するデジタル・トランスフォーメーション(DX)の必要性について指摘しています。 しかし、DX推進の向けた日本企業が抱える課題は多く、その課題を克服できない場合はDXが実現できないのみならず、2025年以降、最大で年間12兆円(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性があると予測されています。これを「2025年の崖」と呼んでいます。 それでは、日本企業のDX推進を阻む問題とは何か。その要因の1つは、DXを主導する役割を果たすDX人材・IT人材の不足です。もう1つの要因は、レガシーシステムの問題です。レガシーシステムとは、基幹システムなどを稼働させるメインフレームやオフコンなどのことを指します。構築から既に20年以上経過していても、今なお現役として多くの企業がレガシーシステムを保有しています。 こうしたレガシーシステムは、各企業独自のオーダーメイドで開発したものが多く、企業を取り巻く社会や法令の変化に応じて必要な修正や追加を繰り返し対応してきた経緯があります。その結果、システムは非常に複雑な構成となってブラックボックス化し、DXを実現のためのデータ活用を上手くできないという問題を生じさせています。 データの活用はDXの要であるため、DX推進のためにシステム全体の見直しを迫られる企業も少なくありません。しかし、システム全体を刷新するとなると膨大な投資が必要になると想定され、経営戦略の模索を続けているなかにおいてDXの実現性や投資対効果への不安感から、DX投資になかなか踏み切れないという実情もあるようです。 オフショア開発ニーズの変化、コスト削減と高度IT人材の確保 世界的に見ても、DX推進は企業にとって急務とされています。 しかし、日本国内では、少子高齢化の影響によりIT人材の確保が容易ではない状況が続いています。ベテランエンジニアの退職や高齢化は年々進んでいる一方で、若年層エンジニアもレガシーシステムに関する業務に魅力を感じておらず、稼働を続けているメインフレームの担い手も減少しています。 さらに、AI、IoT、ブロックチェーン等の先端技術の活用が望まれるなか、そうした最先端技術に対応できる先端IT技術者もまだまだ不足しています。一部において、若年層エンジニアに対する先端技術教育や、ベテランエンジニアが最先端技能を学び直せるリスキリング環境の整備などが進められているものの、海外と比較すればそのスピードの遅れはめません。また、既に高度な先端技能を保有する即戦力となる先端IT技術者の人件費も高騰している状況があります。 こうした背景から、国内では確保しづらい先端IT技術者を海外に求める動きが活発化しており、オフショア開発はそうした動きの1つにもなっています。 先述のとおり、かつてのオフショア開発のイメージと言えば、その主な目的が開発コストの削減であったため、開発プロセスにおいては相対的に付加価値の低い中流から下流工程を分業化して、安い労働力を活用しようというものでした。そのため、オフショア開発企業への委託内容は、基幹システム開発の下請けとして上流工程以下のプロセスであったり、Webやスマートフォン等のアプリケーションフレームワークを活用した開発などが中心でした。 ところが現在、日本企業のオフショア開発へのニーズに変化が現れており、それに対応するオフショア開発企業も増えつつあります。昨今では上流工程から製造工程までの開発プロセスを一貫してオフショアで開発することや、アジャイル開発モデルへの対応、レガシーシステムのモダナイゼーションやマイグレーション、またAI、IoT、ブロックチェーン、Web3などの先端IT技術領域までオフショア開発を活用する動きが見られるようになっています。 今回は以上です。 本ブログでは、オフショア開発に関するお役立ち情報や、IT業界で注目を集めている話題をテーマとして多様な情報をお届けしています。 オフショア開発にご興味のある方は、『オフショア開発とは|メリット・デメリット・成功に導く6つのポイント』の記事も是非ごご覧ください。 無料eBookのダウンロード 保存版 オフショア開発入門ガイド2023 オフショア開発を始める前の気になる疑問を解決!オフショア開発を検討中の方に向けて、オフショア開発の基本的な知識から注意点までを解説します。 今すぐダウンロード(無料) 無料eBookのダウンロード チェックリストでわかる 失敗しないオフショア開発会社の選び方 オフショア開発会社選びの準備から開発開始まで、多様な角度からチェックポイントを網羅。チェックリストを活用して効率的な選定や基準作りに役立ちます。 今すぐダウンロード(無料)
メールマガジンの登録 個人情報保護方針についてはこちらを必ずご一読ください
デジタルトランスフォーメーションに関する専門家の見識やイベントの最新情報を受信トレイに直接お届けします