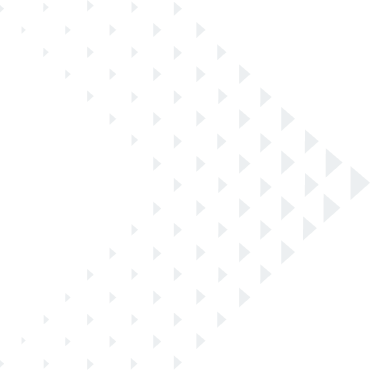ブログ


26/06/2023

3 minutes
Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」によるCXのパーソナライズ化 (P2)
Part 1では、主に広告やマーケティングの文章を効率的に作成するための人工知能を活用した優れたツールである、「Marketing GPT」についてご紹介しました。本記事(Part2)では、同じく生成AI技術を活用したツールである「Commerce GPT」について中心に解説していきます。 「Commerce GPT」とは Commerce GPTは、Data Cloudからのリアルタイムで統合されたデータに基づいて生成された情報を活用し、企業が顧客の購入プロセスのあらゆる段階でカスタマイズされたコマース体験を提供するためのツールです。要するに、Commerce GPTを使えば、企業はデータを活用し、顧客が求める商品や必要な情報を手に入れて、最高の買い物体験を提供できるのです。 Commerce GPTのポイント 信頼できるデータに基づいてトレーニングされたAIを使用することで、ROI(投資利益率)を加速し、より多くの成果を達成し、売上を拡大します。ROIとは、投資した資金に対して得られる利益の割合を表す指標です。つまり、企業はAIの力を借りて投資効果を最大化し、収益を増やすことが可能になります。 リアルタイムかつ統合されたデータを活用することで、顧客の忠誠心が高まり、手間をかけずにダイナミックなショッピング体験や特典、スムーズな購入プロセスを提供できます。つまり、顧客がより満足する買い物体験を手軽に提供することができます。 優れたCRM(顧客関係管理システム)を活用して、お店は顧客とのあらゆる接点で販売活動を行います。販売、サービス、マーケティングのさまざまな手段を使い、柔軟な買い物体験を提供し、顧客が利用している場所に合わせて対応します。つまり、お店は顧客とのつながりを大切にしながら、どこでも買い物ができるようにするのです。 Commerce GPTの特徴 最先端のAI技術を活用したコマース向けツールであり、データ駆動の洞察と推奨事項に基づいてカスタマイズされたショッピング体験を提供するCommerce GPTの特徴は、以下の通りです。 「Marketing GPT」と「Commerce GPT」の今後のタイムライン 現在、重要な役割を果たしているData Cloud for Commerceは利用可能です。そして、Marketing GPTとCommerce GPTは以下のように進行する予定です。 Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」は、競争力のある市場で成功するための重要なツールです。これらのAI技術を活用することで、企業は顧客との関係を深め、成長を促進することが可能です。SalesforceのAI技術はますます進化し続けており、関心と期待が高まっています。今後の展開にはますます注目が集まることでしょう。


23/06/2023

3 minutes
Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」によるCXのパーソナライズ化 (P1)
生成AI、データ(GPT- 4など)、CRMを駆使した大規模なパーソナライゼーションを推進します 。セールスフォース (Salesforce) は最新の技術を活用して、マーケティングキャンペーンとショッピング体験をよりパーソナライズ化を実現する「Marketing GPT」「Commerce GPT」を発表しました。この革新的なアプローチにより、企業は顧客に対してより魅力的なキャンペーンを提供し、ショッピング体験を個別化することができます。 「Marketing GPT」と「Commerce GPT」 Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」は、生成AI技術を活用した革新的なツールです。これらのツールは、顧客の嗜好や行動データを分析し、個別のニーズに合わせたカスタマイズされたコンテンツやサービスを提供します。 「Marketing GPT」とは Marketing GPTとは、広告やマーケティングの文章を効率的に作成するための人工知能を活用した優れたツールです。このツールは、ターゲットの興味を引きつける魅力的なコピーを自動的に生成することができます。マーケティングのプロフェッショナルにとって非常に役立つツールであり、マーケティング成果を最大化するのに大いに貢献するツールです。 Marketing GPTのポイント Marketing GPTの特徴 Marketing GPTは、AIとData Cloudを使って、マーケターが信頼できるデータを使用し、パーソナライズされた体験を提供することができるツールです。具体的な特徴としては、以下のようなものがあります。 1. セグメント作成 データクラウドから入手した信頼性の高い情報を利用し、自然な言葉で質問したりAIが提案してくれるアイデアを活用することで、ターゲットをより具体的に絞り込むことができます。 2.メールコンテンツ作成 Email Content Creationを利用することで、パーソナライズされた電子メールを自動的に作成することができます。これにより、テストやエンゲージメントの向上だけでなく、作成作業の負荷も軽減されます。 3. データクラウドのためのセグメントインテリジェンス Data Cloudのセグメントインテリジェンスを活用することで、マーケティングのROI(収益率)を向上させます。ファーストパーティデータ(自社のデータ)、収益データ、有料メディアのデータを組み合わせて、視聴者の関心をより詳しく知ることが可能になります。つまり、より効果的なマーケティングを行うために、大切な情報を自動的に結びつけて分析することが可能になります。 4. 迅速なアイデンティティの解決、セグメンテーション、エンゲージメントの実現 適切なタイミングで適切なメッセージを届けます。これにより、顧客の情報が自動的に整理され、Data Cloudの情報も最新の正確さで更新されます。つまり、顧客のIDを迅速に特定し、興味や属性に合わせたメッセージを送ることが可能です。 5. Typefaceの生成型AIコンテンツプラットフォームを活用します Typefaceの生成AIコンテンツプラットフォームを活用することで、特定のブランドの声やスタイルガイド、メッセージに基づいて、Marketing GPT内のマルチチャネルキャンペーンに適したビジュアルアセットを作成します。これにより、ブランドの一貫性を保ちながら、視覚的に魅力的なコンテンツを効率的に生成することが可能です。 結論Marketing GPTは、データやAIを活用して個別の顧客に合わせた情報やコンテンツを提供し、顧客によりパーソナライズされた体験を提供します。 具体的には、セグメント作成やメールコンテンツ作成によるターゲット絞り込み、データクラウドのセグメントインテリジェンスの活用により、マーケティングのROI向上が可能です。また、迅速なアイデンティティの解決とエンゲージメントの実現、Typefaceの生成型AIコンテンツプラットフォームによる一貫性の保持が効率的かつ魅力的なコンテンツ生成に寄与します。 これにより、顧客のニーズや好みに合わせたサービスを提供し、顧客満足度を向上させることが可能です。 Part2では、Commerce GPTについて詳しく解説します。 Part 2: Salesforceの「Marketing GPT」と「Commerce GPT」によるCXのパーソナライズ化 (P2)


09/06/2023

3 minutes
Mendixとローコードプラットフォームの力 • アプリケーション開発の未来
Mendix は、モバイルおよびWebアプリケーションを大規模に作成、デプロイ、保守、改善することができるオールインワンのローコードプラットフォームです。 アイデア出しからデプロイメント、メンテナンスの段階まで、アプリケーションの配信プロセスを迅速に進めることができるよう、企業をサポートするように設計されています。 また、クラウドネイティブソリューションとして、作成したアプリケーションをオンプレミスやあらゆるクラウド上に簡単に展開することが可能です。


24/05/2023

3 minutes
Salesforceを活用したデータガバナンスとは?適切なデータガバナンスでデータを管理する
データ管理とガバナンスの重要性は増している ビジネスの拡大やグローバル化が進むにつれて、顧客情報の一元化やデータの保護、管理の重要性はさらに増しています。そのため多くの企業ではSalesforceなどのツールを導入していますが、拡張機能などをいまいち活用しきれていないこともあるのではないでしょうか。また、データの管理や処理、保護はルールやプロセスのもとで適切に行われる必要があるものの、それらを確実に実行するには莫大なリソースと時間がかかります。 そこでこの記事では、Salesforceを最大限活用しながら、データを正確かつ安全、確実なものにするデータガバナンスについてご紹介します。 Salesforceを活用したデータガバナンスとは データガバナンスは、データの正確性や信頼性、完全性、可用性など、データの管理や運用、セキュリティ担保に必要な手順やルールのことを指します。そのプロセスの中にはアクセス制御、バックアップや復旧、標準化なども含まれます。 データガバナンスのメリットとしては、以下の点が挙げられます。 ・データ品質の向上:データガバナンスを導入することで、データの信頼性や正確性を高めることができます。 ・リスクの軽減:データガバナンスがセキュリティやプライバシーに関するリスク軽減の対策そのものになるのはもちろん、データの機密性や整合性を維持することで、企業にとってのリスクを軽減できます。 ・責任の明確化:ルールがあることでデータの所有者や管理者、責任の所在を明確化できます。これにより、データ関連の問題が発生した場合にも「どの時点で、何の責任が発生しているか」をたどることができます。 ・意思決定の改善:データガバナンスによりデータ整理や分類の方法が統一化できることは、意思決定の改善につながります。データの信頼性や整合性が高くなるため、正確な情報に基づいた意思決定が可能となります。 ・コンプライアンスの確保:法律や規制に準拠することが求められる中、データガバナンスはコンプライアンスを確保するためのツールにもなります。企業はデータ保護法や規制に準拠する必要がありますが、データガバナンスの導入によりコンプライアンスの確保がしやすくなります。 データガバナンスのメリットがわかったところで、今度はガバナンスの策定と、Salesforceを活用しながら管理や処理を実行する際の手順、ポイントをいくつかご紹介します。 1. 課題を特定し、ガバナンスを策定する まずはデータを管理する前に必要なルールを策定しましょう。データの属人化やインシデントを防ぎ適切な管理を行うには、組織にある潜在的なリスクを特定した上で運用ルールを決める必要があります。 ちなみに、データガバナンスがルールを指すのに対してデータスチュワードとは「データという財産を適切に管理する人」のことを指します。データスチュワードが不在の場合は、その役割と責任範囲を正しく理解したうえで適切な人材を任命しましょう。 2. データ品質を管理する Salesforceによると、「世界中のマーケティング担当者の約5人中4人が、マーケティング主導の企業成長と顧客体験を実現するための鍵は、データ品質にあると回答しています」*としています。 このことからも、データ品質の管理はセキュリティ担保とマーケティングの両方から重要性を増しています。データ品質の管理には、重複レコードの管理やデータ整合性のチェック、不正データの削除などの定期的な実施が欠かせません。Salesforceでは、データの分類管理を柔軟な整合ロジックに基づいて自動化できます。これにより、空いた時間はインサイトに充てるなどビジネスの効率化が図れます。 3. データアクセスを制御する Salesforceではフィールドレベルのセキュリティ、IPアドレスに基づく制御など、役割に基づいてデータのアクセスが制御できます。適切なユーザーのみが信頼できるデータにアクセスできるように権限を管理する、不正なアクセスを防ぐなど、業界水準に準拠したシステムでデータの機密性とセキュリティを確保しましょう。役割に沿ったアクセス権を付与することは、データスチュワードやマーケティングリーダーが活用するデータの信頼性向上にもつながります。 4. データのバックアップと復旧 大規模災害やインシデントに備え、データのバックアップと復旧を実行することも重要です。Salesforceではプラットフォームの各層にセキュリティが備えられています。またバックアップ方法が複数提供されているため、システム障害やデータの損失に備え、復旧プランを定期的に確認、更新することができます。ネットワークサービスではデータの暗号化と転送機能、高度な脅威検出機能を、 アプリケーションサービスではアイデンティティ管理や認証機能も実装されています。 Salesforce Shieldを通じてさらに信頼性を強化することも可能です。これらのサービスを活用することで、データの可用性と完全性が確保できます。 5. データの標準化 Salesforceではデータの標準化を実行するために、暗号化やバリデーションルールの設定、フィールド値の選択肢の各種設定などが可能です。Shield Platform Encryptionでは取引先の住所や電話番号、商談内容といった標準項目から、フィード投稿やアンケート回答などのフィールド値までが暗号化できます。つまり、標準化によりデータはクリーンで使いやすく整合性が取れたものとなり、さらにセキュリティも向上させることができます。 まとめ テクノロジーが進歩し、顧客やユーザーのニーズも多様化する中、現代のビジネスをより安全に効率よく運営していく上でデータの正確性や信頼性は欠かせないものとなっています。しかし、ここまでご紹介したSalesforceの各種サービス、機能を活用することで、膨大なデータをより適切に管理、活用することが可能となります。組織が持つ課題を特定した上でガバナンスを構築し、Salesforceの一元化されたデータ管理プログラムを最大限活用してビジネスの成果と価値向上に役立てましょう。


20/04/2023

3 minutes
SES契約と準委任契約、ITエンジニアの契約形態の違いをわかりやすく解説
日本国内におけるITエンジニア不足が進行する中、企業はITプロジェクトを推進するために様々な契約形態を検討し、そして活用しています。本記事では、SES契約、準委任契約、派遣契約といったITエンジニアの契約形態の違いを解説します。さらに、偽装請負の問題にも焦点を当て、エンジニアの適切な雇用形態を理解し、法的リスクを回避する方法についても紹介します。 SES契約とは SESとは「System Engineering Service」の略称で、準委任契約と呼ばれる契約形態の一種です。ITエンジニアの労働力を発注側へ提供するもので、開発エンジニア、ネットワークエンジニア、運用・保守の技術者など、その範囲は多岐にわたります。 原則として、発注側に常駐して仕事をするため、後述する派遣契約と混同されることが多いのですが、契約形態は大きく異なります。 請負契約と準委任契約 エンジニアの契約形態には、大きく分けて請負契約と準委任契約のふたつがあります。 ・請負契約 業務委託契約のひとつで、委託された開発の成果物を納品することで契約が完結します。働いている期間や人数にかかわらず、成果物が納品されなければ報酬は支払われません。そのため、原則として手戻りの少ないウォーターフォール型開発と相性の良い契約形態です。 ・準委任契約 特定の業務を遂行することを定めた契約です。定められた期間に、定められたエンジニアを確保するという契約形態であることから、成果物の完成が義務にならない点が請負契約と大きく異なります。そのため、細かい方針変更が多いアジャイル型開発と相性の良い契約形態です。 派遣契約との違い 前述のように、SES契約とよく似た契約形態に派遣契約があります。SES契約も派遣契約も、ITエンジニアが客先に常駐して業務を行う点は同じです。ただし、契約の形態が異なるため、誰の指示を受けるのかが大きく異なります。 ・SES契約 エンジニアに指示を出せるのはSES契約を受注した企業です。発注側の企業が細かい指示は出せません。 ・派遣契約 発注側の企業がエンジニアに細かい指示を出すことができます。 SES契約する発注企業側のメリット SES契約をする企業側には主に3つのメリットがあります。 【受託開発のプロジェクト適用例】 (1)人材の採用・育成のコストを省ける SES契約によってエンジニアを活用できれば、求人募集、面接、研修といった採用・育成のコストを省けます。自社でエンジニアを採用し育成しようとすれば、上記のコストがかかるだけではなく、自社が求める分野の人材を即座に採用できるとは限らない可能性もあります。SES契約を利用すれば、求めるスキルを持つ人材を必要なときに得られるのです。 (2)必要に応じてエンジニアを確保できる SES契約なら、求めるスキルを持つエンジニアを、必要な期間と人数だけ確保できます。そのため、余分な出費や手間がかかりません。専門の仲介会社やマッチングサイトなどを利用すれば、必要なスキルや知識、ノウハウを持ったエンジニアを効率よく雇えるでしょう。急にプロジェクトの内容が変わった、メンバーが突然欠けてしまったなどの場合にも対応しやすいです。 (3)仕様変更にも対応できる 請負契約の場合、期日までに成果物を納品するという形態であるため、原則として急な仕様変更などがあった場合に対応できません。しかし、準委任契約のSES契約ならば、「業務を行う」こと自体が契約なため、成果物いかんに関係なく柔軟に対応できます。 SES契約の工数管理は誰が行う? 工数管理とは、ひとつのプロジェクトを終えるまでにどのくらい工数が必要なのかを計算し、進捗状況を把握するために工数を管理することを指します。派遣契約の場合は発注側が工数管理を行いますが、SES契約では、工数管理や勤怠管理は受注側が行います。 SES契約の工数管理を発注側が行うことは、後述する偽装請負という違法な行為とみなされる場合があります。この点に十分注意して、SES契約の工数管理は受注側に任せるようにしましょう。 SES契約で違法とみなされる場合とは SES契約で働いているエンジニアに対して、労働に関する詳細な指示を発注側が行っている場合は、契約違反とみなされるケースがあります。注意したいのは、SES契約が準委任契約であるという点です。 つまり、派遣契約とは異なり、常駐先の企業(発注側の企業)において、発注側の企業が直接エンジニアに対して指示を出すことはできません。詳しく見ていきましょう。 偽装請負とは SES契約において発注側の企業から直接指示や命令が出されている場合、業務委託契約であるのに労働者派遣や請負契約に偽装しているとみなされます。これは、「偽装請負」と呼ばれる違法行為です。 例えば、SES契約のエンジニアに「何時にどこに行って、こういう作業をしてください」と指示ができるのは、受注側の企業でなくてはなりません。これを発注側の企業から受けてしまうと、偽装請負となってしまうのです。 契約違反を避けるためには、発注側企業と受注側企業との間で、最初に具体的な労働内容を設定する必要があります。設定した契約内容にもとづいて受注側企業がエンジニアに指示を出すのであれば、偽装請負にはなりません。 ・偽装請負が発覚した場合 偽装請負が発覚した場合、労働局から厳しい指導が入り、最大1年の懲役または100万円の罰金という刑事罰が課されるほか、社名公表による信用低下などのリスクがあります。 ・偽装請負を避けるためには 偽装請負を避けるためには、SES契約を結ぶ際に、何をどのように行ってもらうのかを明確に決めておくことが重要です。契約にないことをエンジニアに要求する、自社の規定と契約内容が異なる場合(出勤時間、残業時間など)に無理やり自社の規定に従わせる、といったことは避けなければいけません。 SESは準委任契約であり正しく使ってメリットを生かそう SES契約は準委任契約の一形態であり、発注側の企業に常駐するのが一般的ですが、派遣契約のように発注側の企業から指示を受けることはできません。 SES契約の場合、エンジニアが指示を受けるのはあくまでも受注側の企業です。これを無視して発注側があれこれ指示を出したり、業務時間を勝手に変更したりすると、偽装請負という違法行為と判断される可能性があるため注意が必要です。 SES契約は、ポイントをきちんと押さえればメリットの多い契約です。オフショア開発においてもSES契約は、発注側の企業に常駐して仕事をするため、企業に溶け込みコミュニケーションも円滑になるでしょう。SES契約のオフショア開発をお考えなら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。 【別記事】失敗しないオフショア開発会社の選び方|開発パートナー選定のステップや比較ポイントを解説 株式会社リッケイは、ベトナムを代表するオフショア開発企業の1社であるリッケイソフトの日本法人です。弊社は、日本のお客様に独自の利点をご提供いたします。優れた技術スキルとコスト効率の良さを兼ね備え、ビジネス拡大や効率化に貢献いたします。また、日本国内に4拠点(東京・名古屋・大阪・福岡)を置き、良好なアクセス性とコミュニケーションの円滑さ、文化的な共通性、タイムゾーンの近さなどを通じて、お客様に信頼性と安心感をご提供いたします。 オフショア開発をご検討の際は、どうぞお気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちらから 無料eBookのダウンロード 保存版 オフショア開発入門ガイド2023 オフショア開発を始める前の気になる疑問を解決!オフショア開発を検討中の方に向けて、オフショア開発の基本的な知識から注意点までを解説します。 今すぐダウンロード(無料) 無料eBookのダウンロード […]


17/04/2023

3 minutes
ローコード開発ツール・プラットフォームを選ぶポイントは?おすすめのツールを10種紹介
ローコード開発ツールは、部品を組み立てるようにしてアプリケーションを開発できるツールです。コーディングをあまり行わないので、専門家でなくてもアプリケーションを開発できます。そのため、エンジニア不足の解消や開発スピードの向上、現場のニーズのくみ上げにもつながります。


11/04/2023

3 minutes
おすすめのノーコードツール10選―開発の目的別に特徴・機能を比較
ノーコード開発は、コーディングの知識や技術がなくてもシステムやサービスの開発が可能です。こういったノーコード開発をするとき、重要となるのが使用するノーコードツールの選び方です。用途ごとにおすすめのノーコードツールをご紹介します。


10/04/2023

3 minutes
Lightning Platformとは?Sales Cloudとはどう使い分ければいいのか
Lightning Platformは、Salesforce上で動作するアプリケーションを開発できるローコード開発ツールです。開発したアプリケーションを実行、運用保守、管理するプラットフォームでもあります。ここでは、Lightning Platformの基本的知識について幅広く紹介します。


27/03/2023

3 minutes
受託開発とは?メリット・デメリット、オフショア開発での受託プロジェクト例
ビジネス環境の急速に変化やテクノロジーの進化によって、競合力の維持が課題となる中、様々な開発アプローチが模索されています。各種の開発手法における提柔軟性と効率性はどの方法が最適か、多くの企業にとって重要な戦略的オプションとなっています。 本記事では、受託開発に焦点を絞り、その要点やメリット・デメリット、受託開発の流れを解説するとととに、オフショア開発によって行われている受託開発プロジェクトについても紹介します。 自社開発と受託開発 自社開発と受託開発は、ソフトウェアやプロジェクトの開発方法論に関する2つの異なるアプローチです。企業はプロジェクトの性質や企業の戦略に応じて自社開発と受託開発を組み合わせて使用することで、効果的なソフトウェア開発に効果を発揮します。 自社開発とは 自社開発は、企業が自社の内部リソースを使用してソフトウェアプロジェクトを設計、開発、運用する方法です。企業はソフトウェア開発の全体のプロセスを管理し、プロジェクトに直接関与します。開発者は会社の従業員となります。 自社開発は、自社内に開発チームを組織し、自社製品やカスタムアプリケーションを開発し、自社のビジネスニーズに合わせて柔軟に対応する場合に行われます。 受託開発とは 受託開発とは、企業などの委託主(クライアント)が、自社のプロジェクトやソフトウェア開発に関する特定のタスクや作業を、外部の専門的な開発会社や個人(受託先、開発者、ベンダー)に委託する方法です。 クライアントは開発会社に対してプロジェクトの要件や仕様を提供し、開発会社はそれを実装し、クライアントに成果物を提供します。受託開発は、専門的なスキルやリソースにアクセスするため、自社開発では不足している場合や一時的なニーズに対処するために利用されます。 受託開発は、ソフトウェア開発、ウェブ開発、モバイルアプリ開発、データ分析、品質保証など、さまざまなIT関連プロジェクトに適用されます。 また、受託開発は、フルスクラッチ開発以外の依頼も可能です。受託開発は、新規のソフトウェアプロジェクトを完全に新たに開発するだけでなく、以下のような様々な形態のプロジェクトにも適用されます。 【受託開発のプロジェクト適用例】 (1)既存システムのカスタマイズ 既存のソフトウェアやシステムに特定の機能追加や変更を加えるために受託開発を依頼することがあります。これにより、既存システムを新しい要件に適応させることが可能です。 (2)既存プロジェクトのサポート 既存のプロジェクトやアプリケーションの保守、運用、トラブルシューティング、アップデート、セキュリティパッチの適用など、サポート関連の作業を受託開発に委託することがあります。 (3)アプリケーションの移行やマイグレーション 既存のアプリケーションやデータを新しいプラットフォームに移行するための受託開発プロジェクトも一般的です。これはデータベース移行、クラウド移行、ハードウェアの更新などを含みます。 (4)サードパーティ製品の統合 サードパーティのソフトウェア製品やAPIを既存のシステムに統合するためのカスタム開発が必要な場合、受託開発を利用します。 (5)テストと品質保証 ソフトウェアテストや品質保証作業を外部の専門家に委託することがあります。特に大規模なプロジェクトでは、独立したテストチームが品質管理を行います。 受託開発は、新規開発だけでなく、既存のソフトウェアやプロジェクトの拡張、改善、保守、統合などにも適用され、クライアントの特定のニーズに合わせてカスタマイズされることが一般的です。 受託開発のメリットとデメリット 受託開発の主要なメリットとデメリットは、主に以下の通りです。 受託開発のメリット ・専門知識の活用 開発会社は技術的な専門知識と経験を持っており、クライアントはその専門知識を活用できます。これにより、高品質で効率的なソフトウェア開発が可能です。 ・コスト削減 開発会社は設備やリソースを共有できるため、クライアントは自社での開発に比べてコストを削減できます。また、受託開発会社は人件費などのリソースに関する管理も行います。 ・コアビジネスに専念できる クライアントはソフトウェア開発に関するすべての責任を開発会社に委託できるため、自社のコアビジネスに専念できます。 ・スケーラビリティ 開発会社はプロジェクトの規模や要件に応じてリソースをスケールアップまたはダウンでき、柔軟性があります。 ・リスク分散 開発会社はプロジェクトのリスクを共有し、問題が発生した場合にも対応できる体制を持っています。 ・フルスクラッチ開発の自由度 受託開発では、ソフトウェアをフルスクラッチで開発できるため、機能や仕様に関して自由度が高いです。クライアントの要求に合わせてカスタマイズされたソリューションが提供されます。 受託開発のデメリット ・コミュニケーションの課題 クライアントと開発会社の間で適切なコミュニケーションが確保されない場合、要件の誤解やプロジェクトの方向性のずれが発生する可能性があります。 ・品質管理の難しさ クライアントは開発の進行状況をリアルタイムで把握しづらいため、品質管理やテストの監視が難しい場合があります。 ・コントロールの喪失 開発会社がプロジェクトの制御を握っているため、クライアントは一部の意思決定権を委任しなければならない場合があります。 ・細部の把握の難しさ クライアントは開発の詳細なプロセスや技術的な側面について十分な知識を持っていない場合、プロジェクトに対するコントロールが難しくなる場合があります。 ・契約や法的な課題 契約や法的な問題が発生する可能性があるため、契約書の明確な取り決めが必要です。 受託開発の流れ システム開発における受託開発の一般的な開発フローは以下の通りです。 1. システム構築の検討・決定 システム構築の必要性を検討し、社内での検討と決定プロセスを実施します。どのようなシステムが必要か、現行システムの制約事項、パッケージソフトウェアやクラウドサービスの適用可能性などを評価します。 […]
メールマガジンの登録 個人情報保護方針についてはこちらを必ずご一読ください
デジタルトランスフォーメーションに関する専門家の見識やイベントの最新情報を受信トレイに直接お届けします